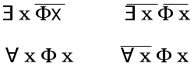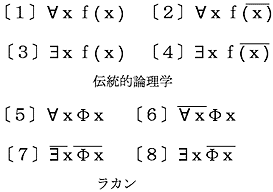の補足資料である。
ジジェク『How to read Lacan』より(鈴木晶訳p193~)一部、原文を挿入したが、特に意味はない。和訳ですぐさま理解できなかった箇所を原文を参照したまでである。
ラカン的な視点からすると、最も根源的な見かけとは何か。妻に隠れて浮気をしている夫を想像してみよう。彼は愛人と密会するときは、出張に行くふりをして家を出る。しばらくして彼は勇気を奮い起こし、妻に真実を告白するーーー自分が出張に行くときは、じつは愛人と会っていたのだ、と。しかし、幸福な結婚生活といううわべが崩壊したとき、愛人が精神的に落ち込み、彼の妻に同情して、彼との情事をやめようと決心する。
※こういったメカニズムはよくあるパターンであって、愛人の欲望は、他者の所有物への欲望であったに過ぎず、つまりは禁止されていることによる欲望(幸福な結婚生活をしている<男>を愛することは禁じられているので、そのために欲望する)が、実際に実現されそうになると、拍子抜けして、身をひいてしまう。ジジェクは「精神的に落ち込み」などと書いているが、このあたりのことはよくわかっているはずで、ただ論旨・文脈とは違うので、簡便に書いているに過ぎない。以下、上記の引用の続きに戻る。
妻に誤解されないようにするためには、彼はどうすべきだろうか。出張が少なくなったのは自分のもとに帰ってきたからだと妻が誤解するのを阻止するには、どうすべきだろうか。情事が続いているという印象を妻に与えるため、彼は情事を捏造し、つまり二、三日家を空け、実際には男友達のところに泊めてもらわなくてはならない。
これこそが最も純粋な見せかけである。見せかけが生まれるのは、裏切りを隠すために偽りの幕を張るときではなく、隠さなくてはならない裏切りがあるふりをするときである。この厳密な意味において、ラカンにとっては幻想そのものからして見せかけである。
見せかけとは、その下に<現実界>を隠している仮面のことではなく、むしろ仮面の下に隠しているものの幻想のことである。したがって、たとえば、女性に対する男性の根本的な幻想は、誘惑的な外見ではなく、この眼も眩むような外見は何か計り知れない謎を隠しているという思い込みである。
From the Lacanian perspective, what then is appearance at its most radical? Imagine a man having an affair about which his wife doesn’t know, so when he is meeting his lover, he pretends to be on a business trip or something similar; after some time, he gathers the courage and tells the wife the truth that, when he is away, he is staying with his lover. However, at this point, when the front of happy marriage falls apart, the mistress breaks down and, out of sympathy with the abandoned wife, avoids meeting her lover. What should the husband do in order not to give his wife the wrong signal? How not to let her think that the fact that he is no longer so often on business trips means that he is returning to her? He has to fake the affair and leave home for a couple of days, generating the wrong impression that the affair is continuing, while, in reality, he is just staying with some friend. This is appearance at its purest: it occurs not when we put up a deceiving screen to conceal the transgression, but when we fake that there is a transgression to be concealed. In this precise sense, fantasy itself is for Lacan a semblance: it is not primarily the mask which conceals the Real beneath, but, rather, the fantasy of what is hidden behind the mask. So, for instance, the fundamental male fantasy of the woman is not her seductive appearance, but the idea that this dazzling appearance conceals some imponderable mystery.
このような二重の欺瞞の構造を説明するために、ラカンは、古代ギリシアの画家ゼウキシスとパラシオスの、どちらがより真に迫った騙し絵を描くことができるかという競争を引き合いに出す。ゼウキシスはすばらしくリアルな葡萄の絵を描いたので、鳥が騙されて突っつこうとしたほどだった。パラシオスは自分の部屋の壁にカーテンを描いた。訪れたゼウキシスはパラシオスに「そのカーテンを開けて、何を描いたのか見せてくれたたまえ」と言ったのだった。ゼウキシスの絵では、騙し絵がじつに完璧だったので、実物と間違えられたのだったが、パラシオスの絵では、自分が見ているこの月並みなカーテンの後ろには真理が隠されているのだという思い込みそのものの中に錯覚がある。
ラカンにとって、これはまた女性の仮装の機能でもある。女性は仮面をつけ、われわれ男性に、パラシオスの絵を前にしたゼウキシスと同じことを言わせる……「さあ、仮面をとって、本当の姿を見せてくれ!」(……)
男は女に化けることしかできない。女だけが、女に化けている男に化けることができるのだ。なぜなら女だけが、自分の真の姿に化ける、つまり女であるふりをすることができるのだから。
ふりをするという行為がひたすら女性的な行為であることを説明するために、ラカンは、自分がファルス(男根)であることを示すために作り物のペニスを身につけている女性を引き合いに出す。
ーーーこれがヴェールの背後にいる女性です。ペニスの不在が彼女をファルス、すなわち欲望の対象にします。この不在をもっと厳密に喚起すれば、つまり彼女に、仮装服の下に可愛い作り物のペニスをつけさせれば、あなたがたは、いやむしろ彼女はきっと気に入るにちがいありません。(エクリ)
この論理は見かけ以上に複雑である。それはたんに、偽のペニスが「真の」ペニスの不在を喚起するということだけではない。パラシオスの絵の場合とまったく同じように、偽のペニスを見たときの男の最初の反応は、「そんな馬鹿げた偽物は外して、その下にもっているものを見せてくれ」というものである。かくして男は偽のペニスが現実の物であることを見落としてしまう。女が「ファルス」であることは、偽のペニスが生み出した影、つまり偽のペニスの下に隠されている存在しない「本物の」ファルスの幽霊である。まさしくその意味で、女性の仮装は擬態の構造をもっている。というのも、ラカンによれば、擬態(物まね)によって私が模倣するのは、自分がそうなりたいと思うイメージではなく、そのイメージがもついくつかの特徴、すなわち、このイメージの背後には真理が隠されているということを示唆しているように思われる特徴である。パラシオスと同じく、私は模倣するのは葡萄ではなく、ヴェールである。「擬態は、背後にあるそれ自身と呼びうるものとは異なる何かを明らかにするのです」(エクリ)。ファルスの地位そのものが擬態の地位である。ファルスは究極的に人間の身体にくっついているいぼみたいなもので、身体にふさわしくない過剰な特徴であり、だからこそそのイメージの背後には真理が隠されているという錯覚を生むのである。
a man can only pretend to be a woman; only a woman can pretend to be a man who pretends to be a woman, as only a woman can pretend to be what she is (a woman). To account for this specifically feminine status of pretending, Lacan refers to a woman who wears a concealed fake penis in order to evoke that she is phallus:
”Such is woman concealed behind her veil: it is the absence of the penis that makes her the phallus, the object of desire. Evoke this absence in a more precise way by having her wear a cute fake one under a fancy dress, and you, or rather she, will have plenty to tell us about. [7]”
The logic is here more complex than it may appear: it is not merely that the obviously fake penis evokes the absence of the ‘real’ penis; in a strict parallel with Parrhasios’ painting, the man’s first reaction upon seeing the contours of the fake penis is: “Put this ridiculous fake off and show me what you’ve got beneath!” The man thereby misses how the fake penis is the real thing: the “phallus” that the woman is, is the shadow generated by the fake penis, i.e., the spectre of the non-existent ‘real’ phallus beneath the cover of the fake one. In this precise sense, the feminine masquerade has the structure of mimicry, since, for Lacan, in mimicry, I do not imitate the image I want to fit into, but those features of the image which seem to indicate that there is some hidden reality behind. As with Parrhasios, I do not imitate the grapes, but the veil: “Mimicryreve als something in so far as it is distinct from what might be called an itself that is behind.” [8] The status of phallus itself is that of a mimicry. Phallus is ultimately a kind of stain of the human body, an excessive feature which does not fit the body and thereby generates the illusion of another hidden reality behind the image.
最後にジョン・リヴィエール(Joan Riviere
)「仮装としての女性性」
Womanliness as a Masquerade(1929),International Journal of Psycho-Analysis
の結論部分だけ引用しよう。この論文は当面、未公開となっており、「東京精神分析サークル」HPから会員用のパスワードを取得することで読むことができる。http://psychanalyse.jp/translation-list.htmlri
リヴィエールは、のちにメラニー・クラインなどによって発展される「対象関係」論者のさきがけであり、ラカンは全面的に、この論に賛同しているわけではない。女性性を考える上での、あくまで参考資料である。
明らかになったのは以下のようなことである――彼女は、彼女が至上のものとなり、彼女に害が及ぼされないような状況を幻想のなかで作った。そして、その幻想を作ることによって、彼女は、両親の両方に対しての彼女のサディズム的激怒から帰結する耐え難い不安から自分自身を守ったのだ。この幻想の本質は、両親-対象に対する彼女の卓越性である。それによって、彼女のサディズムが満足させられ、彼女はそれに打ち勝つことが出来た。この卓越性はまた、彼女が両親の復讐を避けることを成功させる。このために彼女がとる手段は、彼女の反応形成と敵対性の隠匿である。このようにして彼女は自らのエス衝動とナルシシズム的自我、そして超自我を同時に満足させることが出来た。幻想は彼女の人生と生活全体の原動力であり、完璧を目指すことを通してそれを成し遂げるという狭い余白に入りこんだ。しかし、この幻想の弱点は誇大妄想的な性格であり、すべての見かけの下で卓越性を必要とする性格である。もし、分析の途上でこの卓越性が真剣に動揺させられたなら、彼女は不安の深遠に陥り、激怒と絶望的なうつ状態になる。つまり、分析の前に病気になってしまうのである。
アーネスト・ジョーンズの同性愛女性のタイプについて一言いっておこう。このタイプの女性の目的は男性に自分の男性性を「承認」してもらうことである。このタイプにおける承認の欲求は、私が記述した症例と違った風に作動している(演じられた任務の承認)としても、同じ欲求の機制と繋がっているのだろうか、という問いが浮上してくる。私の症例ではペニスを所有していることの直接的な承認がはっきりと主張されたわけではなかった。それはペニスの所有がそれらを可能にすることを通してのみ、反応形成を求めた。それゆえ、間接的に、承認はそれでもなおペニスを求めてのことなのである。
この間接性は彼女のペニスの所有が「承認されないように」、言い換えれば「見つからないように」するためだと理解することが出来る。私の患者はペニスを所 有していることを男性に承認してもらうことを公然と求めることにはあまり不安を持っておらず、アーネスト・ジョーンズの諸症例のように、このような直接的 な承認が欠けていることを実際はひそかにひどく嫌がる。ジョーンズの諸症例においては、原初的サディズムがより満足を得ていることは明らかである。つま り、父親は去勢され、自分の欠点を認めすらしている。しかし、これらの女性たちは、どのようにして不安を避けたのだろうか? 母親〔からの報復の不安〕に ついて考えれば、これは当然、母の存在を否定することによってなされる。私が行った諸々の分析の示唆から判断するなら、以下のように結論できる。第一に、 これは原初的なサディズム的要求の移動[displacement]に過ぎず、欲望された対象、つまり乳首、ミルク、ペニスがたちどころに諦められること になる。第二に、承認の欲求は概して赦免の欲求である。いまや母親が辺獄へ追いやられる。つまり、母親との関係はまったく不可能になる。母親の存在は否定 されるために現れるが、母親の存在が恐れられすぎているということが真実である。それゆえ、両親に勝利したことの罪は父親によってのみ赦される。もし父親 が彼女のペニスの所有を認め、認可するならば、彼女は安全である。彼女に承認を与えることによって、父親は彼女にペニスを与え、しかもそれは母親に与える のではなく、その代わりに彼女に与えるのである。彼女はペニスを持つのであり、また持っていてもかまわないのであり、それで全て順調なのである。「承認」 とはつねにある部分、自信回復[reassurance]であり、認可[sanction]であり、愛[love]である。さらにすすんで、承認は彼女を再び至上のものにする。父親がそのことをあまり知らずとも、彼女に対して男性は自分の欠陥を認めることになる。その内容において女性の父親への幻想-関 係は通常のエディプスのそれと似通っている。違いは、それがサディズムという基盤の上に置かれていることである。彼女は母親を実際に殺害したが、それに よって彼女は母親が持っていたたくさんの楽しみから除外されてしまう。そして、それでも彼女は父親から得るものを大いに巻き上げ、引き出す。
……これらの結論は、さらに以下の問いを強いることになる。完全に発達した女性らしさ[femininity]の本質的性質とはなんであろうか? das ewig Weibliche(永遠の女性)とは何か? マスクとしての女性性[womanliness]という概念は、その背後に男性が隠された危険を想定するものであり、謎にわずかな光をあててくれる。
ヘレーネ・ドイチュやアーネスト・ジョーンズが述べたように、完全に発達した女性性は口唇-吸乳期[oral-sucking stage]に発見できる。その原初的秩序の満足は唯一、(乳首、ミルク)ペニス、精液、子供を父親から受け取ることの満足である。それ以外では、満足は諸々の反応形成に依存している。「去勢」の受け入れ、謙虚さ、男性への尊敬は、口唇-吸乳的平面の対象の過大評価からやってくる部分もあるが、主となるのは、後の口唇-噛みつきレベル[oral-biting level]に由来するサディズム的な去勢願望の断念(強度の低下)である。「私はとってはいけない、頼まれたとしてもとってはいけない、それは私に与えられたに違いないのだから」 自己犠牲、献身的愛情、自己否定の能力は、母親的人物、あるいは父親的人物に、彼らからとったものを返済し回復しようという努力を表現している。これはまた、ラッド(5)が高い価値を持つ「ナルシシズム的保護手段[narcissistic insurance]」と呼んだものである。
完全な異性愛への到達がいかに性器性欲と同時に発生するかが明らかになった。もう少し進むなら、アブラハムが初めて述べたように、性器性欲はポスト-アンビヴァレント状態への到達という意味を含んでいる。「正常な」女性と同性愛者の両方が父のペニスと欲求不満(あるいは去勢)に対する反抗を欲望している。しかし、「正常な」女性と同性愛者の違いの一つは、サディズムの度合いと、サディズムが二つのタイプの女性に引き起こす不安とサディズムとの両方を取り扱う力の度合いにある。
※参照:すこし文脈は違うが、ジジェクの同じ「How to read Lacan」よりの引用を付加する。
紳士面した似非フェミニストの<あなたたち>に捧げる。
女性に対する性的嫌がらせについて、男性が声高に批難している場合は、とくに気をつけなければならない。「親フェミニスト的」で政治的に正しい表面をちょっとでもこすれば、女はか弱い生き物であり、侵入してくる男からだけではなく究極的には女性自身からも守られなくてはならない、という古い男性優位主義的な神話があらわれる。
フェミニストを装う男性優位主義者にとって、問題は、女性は身を守れないだろうということではなく、女性は性的嫌がらせを受けることで過剰な快楽を覚えるだろうということだ。男性の侵入が、女性の内部で眠っていた、過剰な性的快感の自己破壊的な爆発を引き起こすのではないかというのである。要するに、さまざまな嫌がらせへのこだわりには、いかなる種類の主体性概念が含まれているかに注目しなければならないのである。
「ナルシシスト的」主体にとっては、他者のすること(私に声をかける、私を見る、など)はすべて潜在的に脅威である。かつてサルトルが言っていたように、「地獄、それは他者である」。侵害の対象としての女性についていえば、彼女が顔や体を覆えば覆うほど、われわれの(男性的)視線は彼女に、そしてヴェールの下に隠されているものに、惹きつけられる。タリバーンは女性に、公の場では全身を覆って歩くことを命じただけでなく、固い(金属あるいは木の)踵のある靴をはくことを禁じた。音を立てて歩くと、男性の気を散らせ、彼の内的平安と信仰心を乱すからという理由で。これが最も純粋な余剰享楽の逆説である。対象が覆われていればいるほど、ちょっとでも何かが見えると、人の心をそれだけ余計に乱すのである。
ということで、私は、「覆えば覆うほど」を、決して「規制すれば規制するほど」などと読み替えるつもりはない……。あるいは「現実に性的暴力」が頻発しているのに何を呑気なことをいっているのか」という反論に対して、たとえば強姦などは性的欲望の問題ではない、支配欲、権力欲の問題であるなどという「常識的な」見解を述べるつもりもまったくない。さらに言えば中井久夫の「いじめの政治学」などを持ち出して、セクシャル・ハラスメントの別の様相をさらに叙述するつもりなど毛頭ない……。